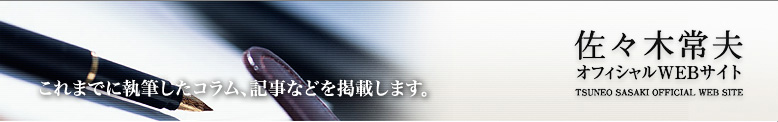
 |
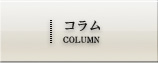 |
 |
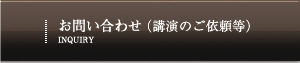 |
| |
| 佐々木常夫流・7つの習慣(その15) 2017.7.17 メンバーの志を一つにするために 組織のミッション・ステートメントを作成する ■自分の部や課のミッション・ステートメントをつくろう ミッション・ステートメントは、「個人のミッション・ステートメント」だけではなく、「組織のミッション・ステートメント」を作成することも可能である。コヴィー氏は、 組織として自分たちのミッション・ステートメントをつくることは「組織の成功にとってとても重要なものになる」(『完訳 7つの習慣 人格主義の回復』P181)と述べています。組織のミッション・ステートメントをメンバーが共有することによって、目的地に向かってメンバーが志を一つにしながら組織という船を動かしていくことができるからだ。 実は日本の多くの会社は、すでに組織のミッション・ステートメントを作成している。それは社是とか社訓と呼ばれるものである。社是や社訓は、会社の経営理念や社会的存在理由、基本方針、社員の行動規範を示したものだから、まさにミッション・ステートメントそのものであるといえる。 ただし現実には、社是や社訓が単なるお題目になっている会社が少なくない。立派な社是や社訓と、日々自分たちがやっていることとが、きちんと結びついていない状態になっているのだ。 社是や社訓が形骸化している場合、リーダーはもう一度のミッション・ステートメントを構築し直す必要がある。ミドル・リーダーであっても、自分が部長や課長を務めている部や課のミッション・ステートメントであればつくることが可能だ。 組織のミッション・ステートメントを作成する際に大切なのは、メンバー全員に「これは上から与えられたものではなく、自分たちのミッション・ステートメントなんだ」という意識をいかに持たせられるかということである。コヴィー氏も次のように述べている。 「組織のミッション・ステートメントが効果的であるためには、その組織の内側から生まれたものでなければならない。(中略)組織のミッション・ステートメントもまた、できあがったものと同じようにプロセスが重要であり、全員が参加することが、ミッション・ステートメントを実践できるかどうかの鍵を握っている」(『完訳 7つの習慣 人格主義の回復』P181) ■組織のミッション・ステートメントを個人レベルに落とし込む 私は組織のミッション・ステートメントをつくったうえで実践するときには、大きく四つのプロセスが必要になると思っている。 まず求められるのは、リーダーが自分自身が考えている組織のミッションをメンバーに示すこと。リーダーは組織のことが一番見えていて、組織を引っ張っていかなくはいけない立場にある。だからリーダーは、自分たちはどんな組織になることを目指すのか、そのために何を大切にしていくのかについて、メンバーに明示できなくてはいけない。 次に大切になるのは、メンバー間のミッションの共有化である。リーダーが示したミッションを叩き台にして、「そのミッションは、自分たちがやるべきことを本当に体現したものになっているか」、「原則から外れたものになっていないか」といったことを、みんなで議論し、検証していく。そして誰もが納得できるところまでミッションを練り上げていく。コヴィー氏が言うように、ミッション・ステートメントづくりに全員が参加することが、これを実践できるかどうかの鍵を握っている。 また組織として掲げたミッションを、個人レベルにまで落とし込んでいく作業も大事だ。コヴィー氏は『7つの習慣』の本の中で、あるホテルのミッション・ステートメントを紹介している。そのホテルでは、自分たちが属しているホテルチェーン全体のミッション・ステートメントとは別に、グループ全体との調和をとりながらも、自分のホテルの状況や環境、現状などに合わせて独自のミッション・ステートメントを作成している。さらに客室係やフロントといった各部署のスタッフも、他部署のミッション・ステートメントとの整合性を考慮しながら、それぞれ独自に自分のたちの部署のミッション・ステートメントを作成している。 つまりホテルチェーン全体の大きなミッション・ステートメントを受けたうえで、それぞれのスタッフが自分の持ち場で、何を大切にしてどんな行動をとるかを、自分たちのミッション・ステートメントとして落とし込むことができているわけだ。こうした組織は、みんなが自発的に一つの目的地に向かって行動できるとても強い組織であるといえる。 そして最後に大切になるのは、反復連打である。ミッション・ステートメントは紙に書いただけでは形骸化する恐れがある。事あるごとにメンバーに読み返すことを求め、実践できているかを確認させることが大事だ。これによってミッション・ステートメントが組織の中に「生きたステートメント」として浸透していく。 第2の習慣…終わりを思い描くことから始める 実践ポイント ■目的地が定まってこそ、効果的に主体性を発揮することができる ■犠牲にしたもののなかに成功よりも大事なものがある ■すべてのものは、まず頭の中で創造され、次にかたちあるものとして創造される ■自分の強み弱み、向き不向きを棚卸する ■一年間の目標をA4の紙一枚に書き出す ■個人のミッション・ステートメントだけでなく組織のミッション・ステートメントもつくる その1│ その2│ その3│ その4│ その5│ その6│ その7│ その8│ その9│ その10│ その11│ その12│ その13│ その14│ その15│ その16│ その17│ その18│ その19│ その20│ その21│ |