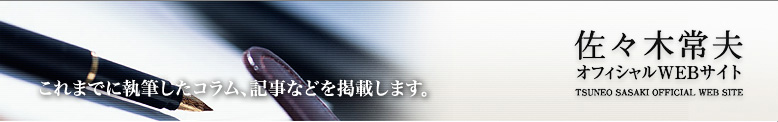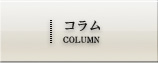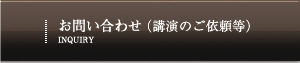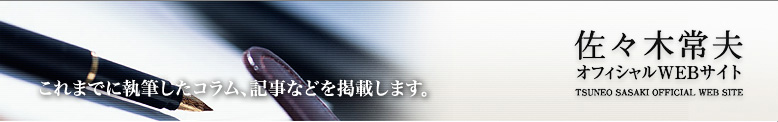ビジネスマンのための論語(15回)
2017.4.4
君子は上達し、小人は下達す
君子は大きなことに通じ、小人は細かなことに通じている。
有能なリーダーを目指すなら、小さなことにとらわれない度量が必要だということである。もちろんそれはそうだが、この章句の解釈には気を付けなくてはならない。 ビジネスをしていて感じるのは、優秀な経営者は大きいことにも通じているが、現場で起こっている小さいこともよく知っているということだ。
私が在籍していた会社の社長は、毎年のように国内外の工場の現場を回ったり、株主総会の前にはスタッフの作成した何百という想定質問のほとんど全てに目を通して、当日どんな質問が出ても答えられるようにしていた。
質問が出ても大方は、自ら答えず担当役員に振ることが多いのだが、経営全般について、最もよく知っていたのはトップであった。 「戦略は細部に宿る」という言葉もあるが、現場で起こっている細かいことも掴んでいるからこそ、大局的に正しい判断ができるとも言える。
私はリーダーにとって最も大事なことは、今現場で何が起きているか、あるいは今経営の最大の問題点は何かなどを正しく掴む現実把握力だと考えている。 今、人は何を求めているのか、社員は何に困っているのか、赤字事業の真の原因は何か、そういった現実を正しく掴めばやるべきことは自然に表れてくるものだ。
正しい現実把握もせず、決断力が大事だといっても、そうした決断はたいてい間違うだけである。
子曰く、中人より以上には以て上を語るべく、中人より以下には以て上を語るべからず
中級以上の能力のある者には、高度なことを教えるのもいいが、そうでない者にはそういう話をしても無駄である。
孔子は平等を装った一律主義はむしろ不平等の原因で、一人ひとりの個性に合わせた教育を提唱している。 仕事が的確にできる人、できない人、意欲を持っている人、そうでない人などさまざまであり、そういう人たちに一律の対応はできないし、無駄である。
その人の個性や能力に応じた対応が必要なのは当然のことである。 しかし、組織を運営する管理者が心得なければならないことは、能力の高い人を活用するだけではなく、能力や意欲の低い人の力を引き上げ、その能力を最大限に伸ばすことがもっと大事だということだ。
能力の高い人は既に高い水準にあるので伸びても10%程度だが、能力の劣る人は、まだ十分開発されていないので20%、30%の伸びしろがある。
ややもすると管理者は、能力の高い人に重要な仕事を集中させる傾向があるが、むしろ能力の低い人のモチベーションと能力を引き上げ、そのことによって組織全体の底上げをすべきである。
私が議員を務めていた男女共同参画会議では「目指すべき社会」とは、「男女の人権が尊重され尊厳をもって個人が生きることができる社会」であり、「男女が個性と能力を発揮することによる多様性に富んだ活力ある社会」と謳っている。
つまり、組織を構成する一人ひとりが、そのレベルに合わせて能力を十分発揮することで、組織の強化を図ろうという考え方である。 ちょっと変わった人でも、少々意欲や能力が劣っている人でも、たとえどんな人であっても、すべての人の力を引き出すことが求められるのである。
第1回│
第2回│
第3回│
第4回│
第5回│
第6回│
第7回│
第8回│
第9回│
第10回│
第11回│
第12回│
第13回│
第14回│
第15回│
第16回│
第17回│
第18回│
第19回│
第20回│
第21回
|