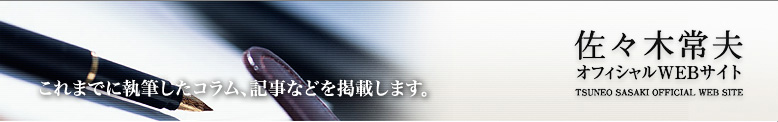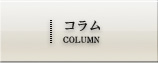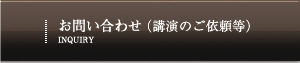ビジネスマンのための論語(11回)
2016.3.24
故きを温めて、新しきを知る。以て師と為るべし
古典で古い学説を学び、そこに現代的な解釈を付け加えてみるといい。そんなことができる人は他人の師となることができる。
ここに孔子のエッセンスが集約されている。孔子は先人への共感と追体験の中に学問の大きなポイントがあると考えた。
真の創造性とは無から有を生み出すことだが、それは凡人には難しい。一から十まで自分で考えることはできない。
過去の誰かの知恵を自分なりにアレンジするのが早い。
物事を考察するとき、まずすでに評価が決まっている何らかの考え方に引っ掛けて考えてみる。これが「温故」。
そしてその上に新たに自分流の解釈を付け加えてみる。これが「知新」。
私は三十代で企画の部署に異動した。そのとき最初に実行したのは書庫の整理である。私の席の後ろに、三十年分ほどのその部署の先輩が作った重要書類が保管されていた。一ヵ月かけて朝から晩まで書類の整理をした。書類の半分を捨て、残すべき資料はカテゴリー別に重要度のランキングを付けてファイルリストを作った。
会社の仕事は同じことの繰り返しである。
上司から仕事の指示を受けたら、そのファイルリストから関連する資料を取り出してきて、そこにある考え方やフォーマット、着眼点などをもらい、最新のデータに置き換え自分のアイディアを乗せる。仕事は早くて出来がいいにきまっている。
例えばそこにあるのが経営会議の資料であれば、途中の落第点のついた資料はなく、残っているのは最後の一番優れた作品だからだ。
こうした先人の知恵を活用することを、私は「プアなイノベーションより優れたイミテーション」と言っている。
定公問う、一言にして以て邦を興すべきこと諸れ有りや。孔子対えて曰く、言は以て是くの若くなるべからざるも、其れ幾きなり。人の言に曰く、君たること難し、臣たること易からずと。如し君たることの難きを知らば一言にして邦を興すに幾からずや
魯の定公が「ひとことで国を盛んにできるということがあるだろうか」と尋ねた。孔子が答えた。
「言葉はそうしたものではありませんが、まあ近いものはあります。『君主であることはむずかしい。臣下であることもやさしくない』という言葉です。もし君主であることの難しさが分かるというのであれば、この言葉は一言で国を盛んにするというのに近いのではないでしょうか」
この定公は、やや独断的で家臣の意見を聞くことはあまりなくのちに失脚するが、孔子は君主であることがいかに難しいことかと言っている。家臣であることもまた難しいことだと言っているところも面白い。
やはり国や組織は上に立つリーダーによって、栄えもするし衰えもする。そして組織を率いるリーダーは、今何が起こっているかの現状分析力、周囲の状況がどうなっているかの大局観、これから何が起こるかの洞察力、周囲が付いていこうという人間力などさまざまな資質が求められ、常に目配りしていかなければ方向を誤る。
そういうリーダーになることの難しさを知りながら、リーダーが国の進むべき道を探っていけば国も栄えることになる。
日本は失われた二十年といわれているがそうしてしまった国のトップの責任は極めて大きいといえよう。
第1回│
第2回│
第3回│
第4回│
第5回│
第6回│
第7回│
第8回│
第9回│
第10回│
第11回│
第12回│
第13回│
第14回│
第15回│
第16回│
第17回│
第18回│
第19回│
第20回│
第21回
|