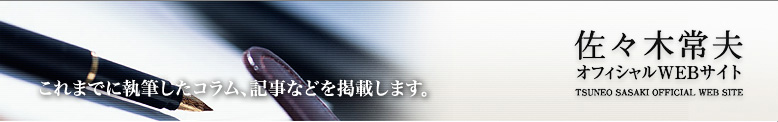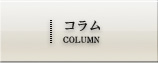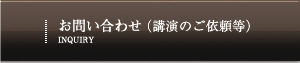ビジネスマンのための論語(10回)
2015.12.23
子曰く、君子は周して比せず、小人は比して周せず
―君子は親しみあうがなれあわない、小人はなれあうが親しみあわない。
または君子は公平でえこひいきしないが、小人はえこひいきして人を公平に見ないという解釈もある。
1924年から4度の外相を務めた幣原喜重郎は秀才の誉れ高く、幣原外交という国際協調路線を主導した。しかし当時の外務省内では、家柄が重んじられ、英語が大の得意で語学の達者な「有能者」には目をかけるが、それ以外の人間には無関心であった。
幣原の部下で後に首相になった広田弘毅は、福岡の石屋の息子という出自で、語学もそれほど優れているわけでもなかったので幣原に疎んじられていた。オランダに左遷されたこともある。
広田は外務省内で滅多に出ない大物との評判があったが、幣原はその評価を認めようとしなかった。
およそ人の能力は一つのことで評価できないし、ましてや人間の器と語学力はあまり関係がない。
もちろん経営者は好き嫌いで人を評価してはならないが、能力といっても語学力があるとか細かいことに気が付くといった点を重宝がって、ついそういう人間を引き上げてしまこともあるから気をつけなくてはならない。
また同じ出身校、同郷、ゴルフやマージャン仲間などと何かにつけて人は群れたがる。
たしかにそうした人間といた方が楽というか、居心地がよいのだろうが、そういうことをしていると組織は弱体化する。
異質な人や異質な考え方を理解して受け入れ、仕事に活かしていくことで組織が活性化し、よい結果に繋がっていくものだ。
これをダイバーシティ経営という。
子曰く、君子は和して同ぜず、小人は同じて和せず
―君子は和を尊ぶが付和雷同はしない、反対に小人は群れるばかりで協調しない。
組織の中で行動するとき、大事なのは構成メンバーひとりひとりを大事にすることだ。意見の対立はあっても争いはしてはならない。喧嘩はしないほうが得策である。
人は性格も価値観もそれぞれ違うし、それを尊重してお互いに切磋琢磨して、組織として結果を出すようにしなければならない。
聖徳太子の十七条の憲法は「和をもって貴しとなす」という。
ビジネスマンにとって大事なのは、どう和するかということだ。
しかし、過度の和、過度の気配りはかえって会社を間違った方向に導く。
少しくらいのことには波風を立てなくてもよいが、会社には組織運営上これだけは守らなくてはならないというコンプライアンステーマがあり、それを守るには、「和をもって貴しとなす」で済ませてはならない。
「和」を重んじつつ、肝心要のことは「同ぜぬ」スタンスが求められる。
第1回│
第2回│
第3回│
第4回│
第5回│
第6回│
第7回│
第8回│
第9回│
第10回│
第11回│
第12回│
第13回│
第14回│
第15回│
第16回│
第17回│
第18回│
第19回│
第20回│
第21回
|