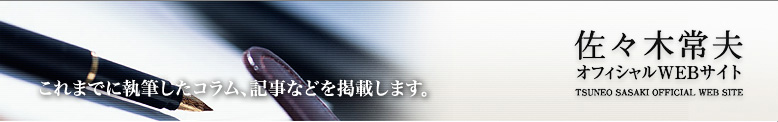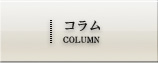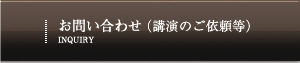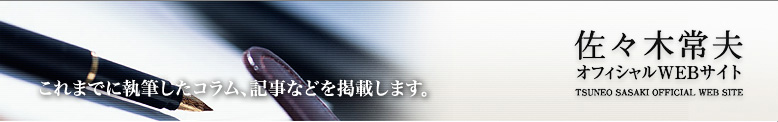| |
 |
| なぜ駒大苫小牧は強いのか 〜徹底的に考え抜こう〜
|
2007年1月 |
|
 |
甲子園にみる勝利への方程式
昨年の甲子園は3連覇を狙う駒大苫小牧を早稲田実業が破って優勝しました。5000校もの甲子園を目指す高校がある中でどうして特定の高校が3連覇を狙えるような実力がつくのでしょう。
駒大苫小牧に入学してくる新入生が最初から他の高校の生徒に比較してかけ離れた実力があるとは思えません。
そんな生徒たちが甲子園に出場できるような実力になるには理由があります。
バントや盗塁などを確実に身に付けさせる練習方法やスケジュール作り、また生徒の個性を見出し伸ばす育成方法、さらにメンタル面での訓練などが他校より優れているからで、これは監督やOBの指導力でしよう。それによって生徒の力を最大限に引き出し勝てるチームを作り上げるというつまり勝利への方程式ができているからだと思います。
数学の苦手な高校生をクラスのトップに
私は大学時代に数学の苦手な高校2年生の家庭教師を頼まれたことがあります。その子の実力を評価した後、私が最初にしたことは中学1年から3年までの教科書をもう一度やり直しし「数学の問題には答えに到るパターンがありその解答のパターンを覚える暗記科目である」と教えそのパターンを繰り返し暗記させました。中学の教科書を3ヶ月で終え、次に高校1年の教科書を2ヶ月かけ復習しましたが、このころには彼は数学の問題を解く面白さにはまっていました。
そして最後は高校2年の教科書に移り彼は極めてスピーディにマスターしていきました。
3学期、数学が苦手だった彼はついにクラスのトップに躍り出たのです。
そのことが彼の自信につながり、他の科目も成績が伸び、最後は本人も家族も思っても見なかった慶応大学にストレートで合格してしまいました。
その高校生の成績が悪かったのは彼の数学の能力が無かったからではありません。勉強の仕方あるいは教え方が不適切だったからです。
勝利への方程式を内蔵する企業は強い
会社の業務も同じで仕事ができるかできないかは能力の差より仕事のやり方の差が大きいのです。
能力の差は考え抜く努力と工夫によって克服できます。通常は会社の先輩が仕事のやり方を教えるべきでしょうが残念ながら多くの企業ではそれができていません。
ところが優れた仕事のやり方や考え抜く力を会社の中にビルトインしている企業がときどきあって他の会社があまり実行していないだけにそういう会社は極めて強い競争力を持つことになります。そのような会社の例がIBMであったりトヨタであったりしますが、例えばトヨタなどは現場からの改善提案は年間60万件でそれだけ多くの提案をする会社のシステムや社員のモラルもすごいですが、もっと驚くのはその提案の実行率が91%だということです。
トヨタ方式なるものは巷で散々喧伝され、トヨタに関する本も多いのですが、読んだ人はたいていの場合感心するだけで自分の会社に合わせた手法に落とし込まないため効果の無いものに終わってしまっています。
私は過去の自分の業務を通じて成果に結びつける仕事のやり方を実証的に研究しこうすべきだという「仕事の進め方10カ条」というものを策定し今までの職場で常に提唱してきました。その内容は計画主義かつ重点主義、効率主義、フォローアップの徹底などで、要は「すぐ仕事にかかるな。もっと頭を使え、考え抜け」ということです。しかし、その通りに実行する部下のなんと少ないことか。そうだそうだと頭では理解してくれていても、考え抜いて自らの仕事に反映できる人、実行できる人は本当に数少ないのが現実です。
所詮「わかること」と「できること」とは全く別なことなのでしょう。 |
佐々木常夫
(ささきつねお)
2001年、東レ同期トップで取締役となり、2003年より東レ経営研究所所長となる。
何度かの事業改革の実行や3代の社長に仕えた経験から独特の経営観をもち、現在経営者育成のプログラムの講師などを実践している。
一方、社外業務としては経団連理事、内閣府や総務省の審議会委員、大阪大学客員教授、神戸大学・同志社大学・桜美林大学の講師などの公職も歴任する。
著書 「ビッグツリー 私は仕事も家族も決してあきらめない」(WAVE出版) |